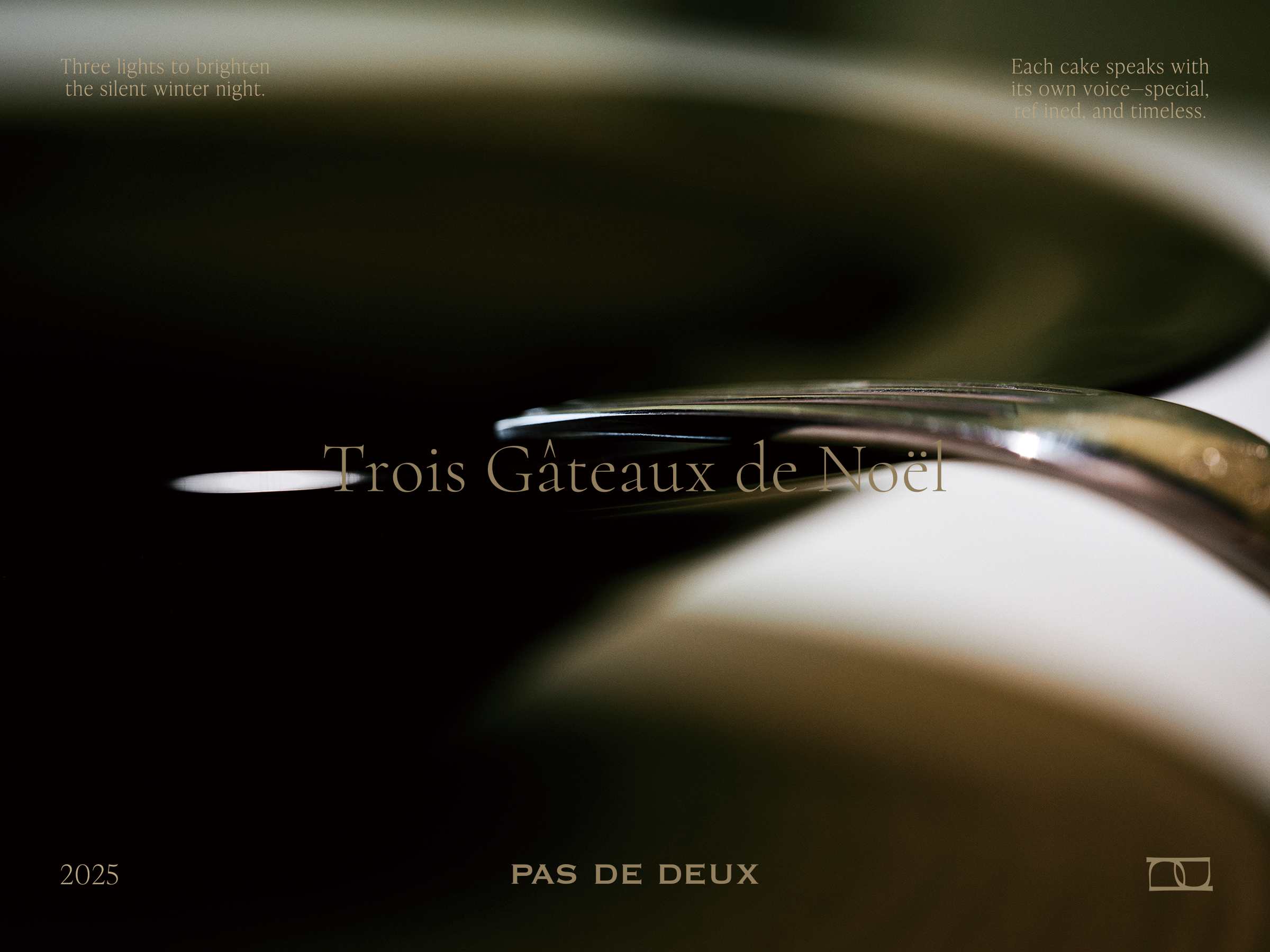From the Source #01 青森県 ヤマサンりんご園 2025/10
秋から冬にかけての美味しいりんご。パドゥドゥでは毎年、青森県のヤマサンりんご園さんから送っていただいています。りんごの収穫前に今さんのもとへお邪魔してきました。
風土との呼応
青森県・北津軽。津軽平野を潤す岩木川と十川のほとりに、風と陽光に抱かれるりんご園があります。岩木山を望むその地で今ご夫妻は日々手を動かします。
探究心を忘れず、実直にりんごに向き合い、小さな命や大地の力と調和しながら、必要なときだけ人の手を添えて育てられる。その営みから生まれるのが、ヤマサンりんご園のりんごです。
冬は雪に閉ざされ、春は風が強く、夏は陽が射す。そんな土地でりんごをつくるには、手際だけでなく、信じ続ける強さが必要です。
雪国で暮らすということは、雪は切っても切り離せません。実際に畑にお邪魔してお話を伺うと、りんごの木が雪で埋まる年もあるといいます。
冷涼な気候と昼夜の寒暖差が必要なりんご作りには雪はとても大切であり、長野や、岩手などのりんごとはまたちがう、青森だからこそできる味わいのりんごになるのかもしれません。
りんごの木とともに歩んでいく家族の姿

三代続くヤマサンりんご園。
風の通り道に沿って並ぶりんごの木々の間を、今さんは進みます。
一歩ごとに、足元から微かな土の香りが立ちのぼり、小柄な奥様でも手が届くように整えられた、個性的な樹形のりんごの木々が目に入ります。ずっしりとした幹に触れながら「これは、おやじと20年前に剪定したときのだな」と、今さんは語ってくださいました。その姿には、時代ごとの家族の想い、夫婦の互いを思いやる日々の歩みが静かに刻まれています。

木を信じて、任せること

枝を整え、葉を一枚残す位置を決め、陽の角度を読みながら実を導く。
感覚ではなく、観察の積み重ね。気温、湿度、風、樹齢、樹皮の質感。すべてが判断の材料になる。その変化を受け止めながら、どうすれば木が無理をせず、最も美しくおいしい果実を実らせるかを探り続けていきます。
一度成功した方法を、翌年もそのまま繰り返すのではなく、観察して、修正して、また観察をしながら、必要なところに手を添えていく。学びを欠かさない。
その“地道なくり返し”に、職人としての矜持があります。

「人が手を加えすぎると、ずっと手をかけてあげなくちゃいけなくなる。
木を信じて任せておけば、勝手にバランスを取ってくよ。」
そう語る今さんのまなざしは、りんごだけでなく、人に対しても同じように向けられています。地域の農家だけでなく、全国のりんご農家や、農業を学ぶ学生、わたしたちのような作り手、互いの知恵を交換しながら、新しいやり方を探っていく。競うよりも、学び合う。
「俺たちはそうやるよ、みんなでやってくなあ」
相手(木でも人でも地域でも)を「変えよう」としない。どう在ればいいのか、調整して、見守る。みんなが今さんを頼りに集まるのがよくわかる。
澄んだ味わいへのつながり

りんごの収穫は9月〜11月が中心。
最近では、技術発展のおかげで、冷蔵庫やCA貯蔵により年中みられるようになったりんごですが、早く食べるのが、香りが豊かで、一番おすすめです。
りんごは、菓子素材としてはとても魅力的な食材。加熱に強いことや、香りが残りやすく、甘いお菓子の中にキレを与えることや、種類が多様性に富んでいて、品種によって香り・果肉感・水分量が異なり、タルトやコンポート、ムースなど多様な菓子に対応できることも作り手としては楽しい食材です。
素材のその先

私たちは、主に「紅玉」を送っていただきます。紅玉の特徴は、小玉で酸味が強いので菓子用に根強い人気がありますが、手間がかかることや、年によるムラが多く収量は少なめです。
今さんの農園に行ってみてとても嬉しいことがひとつ。パドゥドゥ用の紅玉の木を育ててくださっていました。
私たちが伺った時は、少しまだ小ぶりで綺麗なグリーン。これから大きくなり、色づいていくことを感じて、青森とパドゥドゥがつながっているような感覚になりました。そして、今さんの紅玉は、まずその大きさに驚かされます。通常180〜200グラムの小ぶりな紅玉が、今さんの畑では300グラム前後の立派な大玉に育っています。
果肉はしっかりとして香り高く、爽やかな酸味とシャキシャキとした食感が特徴です。その酸味が、甘いお菓子にほどよい引き締まりを与えてくれる。私たちにはなくてはならない秋から冬にかけての食材です。
パドゥドゥでは、紅玉りんごをたっぷり使った『タルトタタン』をはじめ、『焦がしキャラメルとリンゴのムース』『紅玉りんごのパルフェ』などをお作りしています。
焦がしキャラメルとりんごのムースでは、素材本来の魅力を活かすために、シンプルに最低限の砂糖とバター、そして同じくりんごでできたリキュールのカルバドスを少し加えさらに豊かな香りを引き出すように焼き上げます。
りんごの酸味と香りは秋をそっと届けてくれます。


大地と生きものによりそう

今さんとのお付き合いももう15年以上。大地と生きものに寄り添い育まれた、その凛と澄んだ味わいが、心を満たしてくれます。
りんご畑には「カー子ちゃん」と呼ばれるカラスがやってきます。ひとつふたつりんごをかじることはあっても、寄ってくる小さな生きものを追い払い、畑の門番のように見守るそうです。雑草も全部刈ってしまうと虫が木に登ってきてしまうので、少し生えさせておく。
過度に管理するのではなく、自然の力を見つめ、そこに息づく生きものと共にりんごを育てる。
その姿勢に改めて感銘を受けました。自然の恵みや小さな営みへの敬意、素材の個性を生かす手仕事、調和の中での挑戦。
自然と人の知恵が響き合うからこそ生まれるものを信じているのです。そして、何よりもりんごを愛する明るく朗らかなご夫婦のお人柄。食べてくださるお客様のことを想う気持ちがとても強いお二人でした。
今さんの実直な姿勢と技術、“懐の広さ”という言葉に全部詰まっていると感じています。
また、今さんの美しいりんご畑にお邪魔できる日を心待ちにして。
りんごを使った冬のお菓子たちをぜひお楽しみください。
ーーーーー
From the Source
美しい場所には、美しい食文化がある。ご縁のある作り手のみなさんから、ものづくりを学び、大切に受け継がれているものや、手仕事をお伝えしたいと思っています。